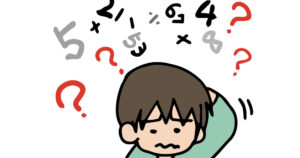小学校で学習する内容は、生きていく上での基礎となる重要なものです。「学習内容の中で必要の無いものは無い」と言っても過言ではありません。しかし、その中でも特に重要なものは何でしょう。
今も昔も、全国どこにおいても、小学校ではほぼ毎日「音読」「漢字」「算数」の宿題が出されます。その理由は、学習の中でも特に重要で、しかも習得に時間・労力がかかるためです。しかし、その時間・労力の程度には個人差があります。学校では標準的にかかる時間をある程度考慮して宿題を出しますが、中にはとても苦労する子がいます。
国語で必ず身につけるべきこと
国語では、宿題に出る「音読」「漢字」の他、読書、書き方、作文等どれを取っても大切な項目です。では、これらの中であえて「必ず身につけるべきこと」を挙げるとすれば、それは何でしょう。ここでは、文部科学省が示している学習障害の視点から、学習指導要領を根拠に見ていきます。
学習障害で困難を示す国語領域
発達障害の1つ「学習障害」には、「医学的」「教育的」の2つの見方があります。文部科学省は、教育的な見方による国語関係で困難を示す領域として、以下の4つを対象としています。
国の組織「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」内の「発達障害教育推進センター」のWebサイトより
- 聞く能力:他人の話を正しく聞き取って、理解すること。
- 話す能力:伝えたいことを相手に伝わるように的確に話すこと。
- 読む能力:文章を正確に読み、理解すること。
- 書く能力:文字を正確に書くこと。筋道立てて文章を作成すること。
つまり「国語で必ず身につけるべきこと」は、まず相手の話や文章を正確に「聞く・読む=インプット」をして理解できることです。そして次に、それを元に相手に伝わるように正確・的確に筋道立てて「話す・書く=アウトプット」ができることと言えます。では、宿題に出る「音読」「漢字」では何が大切でしょう。
音読で大切なこと
音読で重要なことは、上の理由からまず「正確に読めること」です。正確とは「音の正確さ」と「内容の理解の正確さ」のどちらも要素も大切です。よく「気をつけること」として言われる「つっかえずに流ちょうに」は「音+内容の理解」が正確にできるためのものです。「心を込めて読む」は内容を理解した上で読むためのものです。
また、「意味や内容を理解しながら読めるようにすること」も重要です。小学生は、3年1学期で「国語辞典の使い方」を学びます。大人が音読を聞くときは、言葉の意味をときどき質問し、わからない言葉は調べさせることも大切です。「調べる習慣」が身につけば、子どもは自分でわからない言葉を調べて読めるようになります。
そして、音読を通じた「言葉=語彙の習得」は、「話す」「書く」といった「アウトプット」につながります。「語彙」は、正確かつ的確に書いたり話したりするための基礎となります。「漢字」「かな」を問わず正確かつ理解しながら習得し、それらの言葉を使えるように読むことが大切です。
漢字の習得で大切なこと
最近、多くの小学校では「漢字50問テスト」が行われています。このテストは、学校・家庭で「漢字の習得」の目標・確認の材料となっています。ちなみに、小学校学習指導要領には「学年別漢字配当表」が定められていて、下は最新の「各学年で習う漢字の数」です。
第1学年 80字
第2学年 160字
第3学年 200字
第4学年 202字
第5学年 193字
第6学年 191字
小学校学習指導要領(平成29年告示)第2章 第1節 国語 42ページ 別表「学年別漢字配当表」に、具体的な漢字一覧とともに掲載。
これらの漢字は、その学年内に「読み」「書き」両方できなければならないと思いがちです。しかし実は、学習指導要領上では少し違います。小学校学習指導要領「国語」及び中学校学習指導要領「国語」では、次のように書かれています。
(小学校)
第1学年においては、別表の学年別漢字配当表(以下「学年別漢字配当表」という。)の第1学年に配当されている漢字を読み、漸次書き、文や文章の中で使うこと。第2学年においては、学年別漢字配当表の第2学年までに配当されている漢字を読むこと。また、第1学年に配当されている漢字を書き、文や文章の中で使うとともに、第2学年に配当されている漢字を漸次書き、文や文章の中で使うこと。
第3学年及び第4学年の各学年においては、学年別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢字を読むこと。また、当該学年の前の学年までに配当されている漢字を書き、文や文章の中で使うとともに、当該学年に配当されている漢字を漸次書き、文や文章の中で使うこと。
第5学年及び第6学年の各学年においては、学年別漢字配当表の当該学年までに配当されている漢字を読むこと。また、当該学年の前の学年までに配当されている漢字を書き、文や文章の中で使うとともに、当該学年に配当されている漢字を漸次書き,文や文章の中で使うこと。
(中学校)
(第1学年)小学校学習指導要領第2章第1節国語の学年別漢字配当表…に示されている漢字に加え、その他の常用漢字のうち 300 字程度から 400 字程度までの漢字を読むこと。また、学年別漢字配当表の漢字のうち 900 字程度の漢字を書き、文や文章の中で使うこと。
(第2学年)第2学年までに学習した常用漢字に加え、その他の常用漢字のうち 350 字程度から 450 字
小学校学習指導要領(平成29年告示)第2章第1節 国語 第2 各学年の目標及び内容 2内容 知識及び技能(28ページ〜)
程度までの漢字を読むこと。また、学年別漢字配当表に示されている漢字を書き、文や文章の中で使うこと。
中学校学習指導要領(平成29年告示)第2章第1節 国語 第2 各学年の目標及び内容 2内容 知識及び技能(29ページ〜) より
つまり、「小学校で習う漢字をいつまでに習得すべきか」は次のように解釈できます。
「漢字を読むこと」は、その学年までにできるようにする。
「漢字を書くこと」は、小学1〜5年の漢字は次の学年、小学6年の漢字は中学2年までに書けるようにする。
「漢字を文や文章の中で使うこと」は、その学年でも、次の学年でもできるようにする。
「国語で必ず身につけるべきこと」は、まず正確な「インプット」による理解、次に相手に伝わるような正確・的確な「アウトプット」でした。漢字では「インプット=読む」「アウトプット=書く」です。ただし、学習指導要領では「漢字を正しく書けること」は「読めること、使えること」より、習得できるまで1〜3学年分猶予があります。
しかし、実際は「語彙の習得」と「漢字の習得」は関連しています。私たちが語彙を思い浮かべるとき、脳に蓄えられた情報から漢字を引っ張り出す機会は多いと思います。つまり、漢字の習得は「語彙を増やすこと」につながります。猶予期間があっても、できるだけ早く漢字を書けるようになるに越したことはありません。
まとめ
国語で必ず身につけるべきことは、正しく理解しながら「聞く」「読む」、正しく筋道立てて「話す」「書く」ができるようになることです。漢字については「正しく書けること」は若干の猶予がありますが、語彙力につながるため、できるだけ早く覚えたほうが良いと言えます。
学習障害のコラムでも少し触れていますが、それぞれの子どもの特性によって習得に時間がかかる子がいます。項目によっては、思った以上に時間がかかる場合も、かからない場合もあります。それでも、国語の4つの能力は全ての学習の基礎となるため、習得は必要です。特性を見ながら、いかにその子に合ったやり方見出せるかが鍵になります。