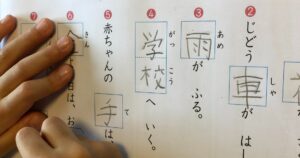「特性」とは、ある「人」や「もの」に特別に備わっている性質のことです。「子どもの特性」とweb上で検索すると、「発達特性」「発達障害の特性」という項目が多くヒットします。確かに、発達障害の子が抱える「他の子と異なる様子」から、特性の具体例を知ることができます。
しかし本来、特性は発達障害の有無(診断も含めて)に関わらず、子どもに限らずさまざまな人が持ち合わせているものです。何か特性があっても特に問題なく過ごせることも、学校生活や勉強がうまくいかないことも、人や場面によりさまざまです。ただし、特性が原因で学習面でつまずくケースがあることは確かです。
ここでは、算数「九九をなかなか習得できない子」に対して、私が実際に行った「特性を踏まえた指導」の体験を書きます。指導当時の知識・経験から試行錯誤して選んだ方法のため、どれも後で振り返ると「他にもっと良い方法があったかもしれない」とも思います。その点も踏まえて読んでいただければ幸いです。
毎年10月頃から、全国の小学2年生は学校で「かけ算九九」を学びます。「かけ算の意味」を理解し、「かけ算九九」を覚えていきます。順番に覚えたら、順番を変えても言えるように指導します。しかし九九は、子どもによっては「決して低くないハードル」で、2年生で習得できずに進級する子がいます。
九九を習得できずに進級すると、その後「算数嫌い」になる可能性が高くなります。「わり算」「2けた以上のかけ算」「小数・分数の計算」「約数・倍数」「分数の通分・約分」…など、九九を使う機会が増えるためです。したがって、なるべく早く「九九を使える程度」にする必要があります。
1. 九九を覚えようとしない子
(具体例)
- 九九のどの段も「〇×1〜〇×3」など、最初の3つくらいまでしか覚えていない。
- そもそも、覚えようとしない。
- ゆっくりでも言えない。
このような子は実は少なからずいます。九九でつまずく要因に「独特の読み方・似ている音」があります。
ふだんと数字の読み方が異なるもの
→4(し)、7(しち)、9(く)、40(しじゅう)、70(しちじゅう)、など
音が似ていて間違えやすい数字
→1(いち)7(しち)8(はち)、4(し)・7(しち)、2(に)・4(し)、など
以前研修で教わったことは、脳にとって「九九を見て、瞬時にその式を音に変換し記憶から答えを導くことはやや高度な処理」とのことです。例えば「8×7」を見て「はちしち」という音に変換し、「はちしちごじゅうろく」という記憶(数的事実)を思い出すことです。
大人側の経験で「自分はそのくらいは頑張って覚えられた」としても、その子が覚えるのにどの程度努力が必要かはさまざまです。仮に何か苦手な特性があった場合、「覚えにくい」「間違える」を繰り返すと、やる気を失うことがあります。
大人側が「やる気が出ない・続かないは本人次第」と自主性に任せておくことで、子どもが自分で解決する場合もあります。しかし、いつまで経っても問題が解決せず、やがて算数嫌いへの道へ進んでしまうこともよくあります。自力解決できるか否かを早めに見極めて、必要に応じて早めの手立て・工夫をしましょう。
指導の方法(例)
大人側が九九を「低くないハードルかも…」と認識し、子どもに合った方法でやる気を引き出すことが求められます。私が実際に子どもたち(2〜4年生)に試した例を、2つ紹介します。
1)スモールステップを作る
やる気が出ない子は、実は「九九を読むこと」自体やっていないことがあります。学校の授業で、クラス全員で九九を唱える時も、先生にしかられないように周りと口の動きや音を合わせているだけで、全く読んでいない子を時々見かけます。
このような子には、スモールステップのチェックカードを作りました。例えば、「九九表を見ながら、声に出して2の段を8秒以内に読む」と、音読課題の欄を作ってみました。音読だけでもできればシールを貼るという欄を1列増やすとどうなるかを試してみました。
結果は、ほとんどの子は「ただ読むだけでシールをもらえるなら…」とやる気を出して取り組むようになりました。シールをもらうと、「次は見なくても言えるようなりたい」と一生懸命取り組み始めました。子どもは実に純粋で、やる気がなさそうに見えても常に「できるようになりたい」気持ちを持っています。
2)同じようなレベルの子をいっしょに取り組ませる。
同じレベルの複数の子を一緒に取り組ませると、お互い刺激し合いやる気が持続する場合があります。具体的には「〇〇くん、6の段合格」「△△さん、7の段合格!」と声かけやシール貼り、ハイタッチ等でほめていくと、本人だけでなくまわりの子も「自分も合格したい」という雰囲気ができました。
〇注意すること
ただし、1)2)の方法はどちらも、方法を選ぶとき、子どもの特性を踏まえる必要があります。以下の2つは、1)や2)が合わなかったケースです。
※「声に出して読むこと」が苦手な子も
「声を出すのが苦手な子」にとって、「声に出して読むこと」はストレスです。また、日本語に不慣れな子にとって、「九九の独特の読み方」はかなりのハードルです。「算数で必ず習得すべきこと」は「九九は覚えて瞬時に正しい答えを出せること」です。算数としては、声に出せなくても瞬時に答えが出せれば大丈夫です。
※「他の子と比べられること」が苦手な子も
子どもの中には「負けを受け入れることが極端に苦手」な特性を持つ子がいて、人に負けたと認識した瞬間「大泣きしてしまう子」もいます。また周りの刺激に弱い子は、他の子と一緒だと集中できなくなることもあります。目標は「九九は覚えて瞬時に正しい答えを出せること」です。そのための最適な場の設定も重要です。
九九を習得することと、それ以外の苦手な面を解決することは、解決までにかかる時間が異なります。無理に一緒に解決しようとせず、分けて考えた方が良いと思われます。
2. 他の刺激に注意が行って集中できない子
(具体例)
- かけ算九九を覚えることより、友だちに勝つことを優先してしまう。
- 教室内の掲示物など、他の物が気になってしまう。
- 友だちの様子が気になり、なかなか自分で覚えることに集中できない。
学校は、たくさんの友だちといっしょに遊んだり学んだりして生活できる、刺激あふれる楽しい場所です。しかし、1でも少し触れたように、刺激に弱い子どもたちにとっては、時にその刺激が悪く働いてしまうこともあります。かけ算九九等「集中して覚えなければならないとき」に、そのような子をよく見かけます。
感覚の特性には、感覚の「敏感・過敏」と、反対の「鈍感・鈍麻(どんま)」があります。子どもによっては、刺激に「過敏」になってしまうことで気が散り、なかなか集中できないケースがあります。最近の学校で「教室前方の掲示物が少ない教室」が多いのは、そうした刺激に弱い子に対する配慮のためです。
このように刺激に弱い子に対しては、刺激の量を調整することで改善する可能性があります。学校に限らず、目、耳など五感から入る刺激を調整した環境を作ることも1つの方法です。
指導の方法(例)
1)刺激に引っ張られない環境で個別に指導
本人はがんばるつもりでも、まわりの子の様子や会話が刺激として入ってきてしまい、がんばりが続かない子がいました。「刺激に対して気持ちが引っ張られる」ことがないよう、別時間に、友だちがいない環境に個別に呼んで指導することで、集中して取り組むことができました。
2)聴覚の刺激を和らげた環境で指導
音の刺激に対して注意が行ってしまい、反応して集中できないことがあります。静かな場所など「聴覚の刺激を和らげる」ことで集中できる場合があります。以前、本人が用意した耳栓をしてある程度雑音を遮断することで、授業に集中できる子がいました。
3)視覚の刺激を和らげた環境で指導
目からの刺激に過敏な場合、目から入る刺激に対して、そちらに注意が行って集中できないことがあります。以前指導した子で、九九を練習してほぼ覚えているのに、検定の時に周りが気になって言えない子がいました。その子に「目を閉じて言ってみよう」とアドバイスすると、言えるようになったことがありました。
〇注意すること
1)〜3)のような可能性があっても、無理やり本人の意志に反した対応をすると、逆効果になる場合もあります。また、刺激を減らすことで、逆にうまくいかない子もいます。大事なことは、本人が納得した方法で「成功体験」を積ませることです。成功体験を積み重ねが、子どもの前向きな意志につながります。
3. 九九を言うペースが上がらない子
(具体例)
- 九九を唱えるスピードがなかなか上がらない。
人が計算するとき、脳のメカニズムは計算の種類により異なる回路を使います。計算の種類は以下の2つがあります。
(1)数的事実(=主に記憶に頼って答えを出すもの)
・一けたどうしのたし算
(例)2+5, 3+6, 5+9
・その裏返しのひき算
(例)7-5, 9-6, 14-9
・かけ算九九
(例)4×6, 2×9, 7×8
・その裏返しのわり算
(例)24÷6, 18÷2, 56÷7
(2)計算手続き(=数的事実より複雑な操作の後で答えを出すもの)
・筆算
(例)132-3, 47×6
・計算のきまり
(例)(28+43)×3
数的事実である「かけ算九九」は、覚え初めの頃は記憶から「意識的に」答えを出します。そして慣れると見た瞬間「無意識的に」答えを出す「自動化」ができるようになります。自動化ができないと、計算手続きが大変になります。
九九の自動化ができない原因は「本人の気持ちの問題」とは限りません。特性によって「覚えるのに時間がかかる子」も「自動化に時間がかかる子」もいます。そのままにしておくと、計算手続きの学習に支障が出て、計算が苦手になる可能性が高いです。早めに見つけ、子どもに応じた手立てが必要です。
指導の方法(例)
1)子ども本人の思い込みを変える
「私は、正しい答えが言えれば、時間はかかってもそれでOK」と本人が思い込んでしまっていることがあります。子どもに「速く」「正確に」どちらも大事と思わせることが重要です。そのような声かけをすることで、考え方を変えてやる気スイッチが入り、できるようになった子がいました。
2)頑張れば達成できそうな目標から 少しずつハードルを上げる
自動化に時間がかかる子でも「練習」を重ねることで、少しずつ速く言えるようになります。とても苦手な子でも、必ず「できるようになりたい」気持ちを持っています。とてもゆっくりでしか言えなかった子に対し、最初の目標を達成できそうな低い設定にして、少しずつハードルを上げて自動化できた子がいました。
3)時間をおいて繰り返し指導
「せっかく自動化できるようになったのに、翌週にはもどってしまった。」ということはよくあります。自動化も定着していないと、使わない期間が空くことで忘れてしまいます。期間を置きながら、根気強く、繰り返し指導することで、必ず自動化は定着に近づきます。
〇考慮すること
「数的事実の自動化」に時間がかかるケースでは、全般的に知的発達に遅れがなくても特定な分野の学習に困難をきたす「学習障害」と診断される場合もあります。教育相談や医療機関などの専門機関に相談してみることも1つの方法です。
ただ、診断がなくてもこのような点でつまずくケースはあります。診断の有無に関わらず、何ができて何ができないかを見極めて、子どもに応じた解決方法を探る必要があります。
まとめ
特性を踏まえた個別指導を行うことで、子どもたちのモチベーションは変わります。子どもたちは、大人が考えている以上に「もっと学びたい」という気持ちを持っています。私たちwillm(ウィルム)では、できるだけ早く、特性を踏まえた適切なフォローをしたいと思います。
子どもたちが何につまずいているかを見つけ、どのような手立てを打つか。子どもの特性に合った指導をすることが重要です。私たちは、このような指導を目指します。
ここまでは、個別の具体的な例として「かけ算九九」をもとに、子どもたちの特性を踏まえた場合にどのような点に注意が必要かを書きました。次回は少し触れた発達障害、特に学習障害についてもう少し触れていきたいと思います。