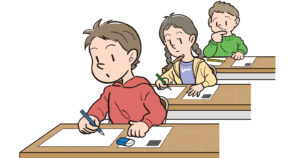人は、何か学習する時に留まらず、生きていくすべての場面で記憶を頼りに生活しています。何かを感じる「知覚」も、何かを考える「推論」も、記憶と深く関わっています。
記憶の3つのプロセス
記憶には「記憶のプロセス」と呼ばれるものがあり、3つの段階があります。
- 覚えること
- 覚えたことを忘れずにいること
- 思い出すこと
ここでは「記憶の分類」と、記憶のプロセス「覚えること」「覚えたことを忘れずにいること」「思い出すこと」ができるようにする方法について書いていきます。
記憶の分類…記憶の保持時間の違いから
記憶にはさまざまな観点からの分類がありますが、ここでは「記憶が保持される時間の違い」による分類を示します。
感覚記憶、短期記憶、長期記憶
「記憶が保持される時間」の観点で分ける考え方として、短い方から順に「感覚記憶」「短期記憶」「長期記憶」の3つがあります。
- 感覚記憶: 目や耳など感覚器官からの情報が、数秒間だけ残る記憶。
- 短期記憶: 感覚記憶の後、短時間だけ一時的に覚えている記憶。リハーサルをしないと数十秒で忘れる。
- 長期記憶: 長時間、長期間、場合によっては半永久的に覚えている記憶。普段は意識に上らなくても、何か手がかりがあれば思い出せる。一度覚えると、数時間から数年、場合によっては一生失われない。
短期記憶には「ワーキングメモリ」という概念が含まれます。この概念は「短期記憶では長期記憶からも情報を引き出し、情報を総合して目の前の課題を遂行する」という考え方です。例えば「先生の話を聞きながら、内容を整理してノートに書く。」とき、脳はワーキングメモリとして、能動的・フレキシブルに情報処理を行っています。
覚えるべきことは「長期記憶」に
このように、物事を考え行動するためにはワーキングメモリを使います。そして、ワーキングメモリを働かせるためには、「短期記憶」と考え行動するために必要な情報「長期記憶」が必要です。したがって覚えなければいけないことは「長期記憶」にして、忘れないように定着させることが重要です。
覚えるために、覚えたことを忘れずにいるために
長期記憶として覚え、それを忘れないようにするためにはどうするべきでしょう。心理学の観点では、「リハーサル」「間を入れながら覚える」などが有効とされています。
忘れないように繰り返し唱える「リハーサル」
心理学の観点では、何かを覚えて忘れないようにするために繰り返し唱えることを「リハーサル」と言います。「声に出す」「頭の中で」のどちらの方法も含みます。主なものとして以下の種類があります。
- 維持リハーサル
「単なる復唱」など、機械的に繰り返し覚えること。 - 精緻(せいち)化リハーサル
「ゴロ合わせ」「ストーリー化」「カテゴリー化」など記憶項目に工夫を加えて、情報と知識を関連付けて覚えること。 - 視覚的リハーサル
「視覚的に思い浮かべる」など、記憶項目をイメージに変換させて覚えること。
「維持リハーサル」は、短期記憶としての保持しかできないと言われています。長期記憶として確実に定着するためには、「精緻化リハーサル」「視覚的リハーサル」等リハーサルの工夫が必要です。また「自己参照効果」といって「自分事との関連付けで覚えることも有効」という研究があります。
「間」を入れながら覚える
記憶を定着させるためには、脳をただひらすら使い続けて覚えるより、「間」を入れながら覚えた方が効果的と言われています。例えば「間欠リハーサル」という方法があります。リハーサルとリハーサルの間に数分、数日、数か月、…と「間」を入れながら覚えると、連続してリハーサルするより効果的なことがわかっています。
思い出すために
覚えたことを思い出すためには、思い出しやすくするための工夫が必要です。心理学な観点から、2つの項目を挙げます。
覚えた後に「脳を休ませる」
記憶には、「覚えた直後」より「覚えて一定時間経過した後」の方がよく思い出せることがあります。このような現象を「レミニセンス」といいます。 一定時間を置く間に、脳は「不要な情報を削除」したり「必要な情報だけ長期記憶に送る」など、情報の整理がされます。
また「眠っている時」や「休んでいる時」も、脳では記憶を整理する活動が行われていることがわかっています。例えば、ボーッとしている時も脳全体の神経ネットワーク活動が行われています。この活動は「デフォルト・モード・ネットワーク」と呼ばれ、「情報の整理」だけでなく「いろいろな記憶をつなぎ合わせて新たな発想を生み出す」と言われています。
このように、覚えたことを思い出しやすくためには、覚えることに使った脳に「覚えた後に適度な休みを与える」ことも重要です。
思い出すための「手がかり」
何かを思い出そうとするとき、その何かが喉元まで出かかっているのに思い出せないことがあります。覚えたことを思い出せないのは、記憶が無くなったわけではなく「手がかり」さえあれば思い出せる可能性があります。記憶はさまざまな情報と結びついているため、それら情報の一端に触れさえすれば、手掛かりとなって思い出す可能性があります。
例えば覚えたときの「文脈や感情」は、思い出す時に同じ「文脈や感情」だと思い出せる場合があります。また「精緻化リハーサル」や「視覚的リハーサル」など覚えるときの工夫も、その手がかりに十分なり得ます。覚える際にいろいろな手がかりを付けながら覚えることも重要です。
まとめ
私たちが「考え、行動する」ために、記憶は必要不可欠です。記憶の3つのプロセス「覚えること」「覚えたことを忘れずにいること」「思い出すこと」ができるように、記憶にどのように取り入れ、取り出せるようにするかが重要です。
そのために、まずは「覚えなければいけないこと」はリハーサル方法を工夫しながら確実に「長期記憶」として覚えること。そして、覚えたことが後で取り出せるように多くの手がかりを残しておくこと。思い出す時はその手がかりを見つけることがカギになります。